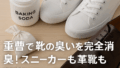リビングは家族みんなが集まる大切な空間。でも、「気づいたら散らかってる…」「掃除するのが面倒…」そんな悩みを抱えていませんか?実は、掃除には“正しい順番”があるんです。この順番を守るだけで、リビング全体が驚くほど効率よく、そしてラクにきれいになります。この記事では、プロも実践するリビング掃除のコツをわかりやすく解説。今日からあなたの掃除がぐんと楽になるヒントが満載です!
\2024年に売れた商品はコレ!/ 楽天ランキングページはこちら<PR>
\人気アイテムをチェックしよう!/ Amazon売れ筋ランキングはこちら<PR>
整理整頓が第一歩!リビング掃除はここから始めよう
不要なものを一時的にどかすのがカギ
リビングの掃除を始めるとき、まず最初にやるべきことは「床やテーブルの上に置かれている物をどかすこと」です。これをやらずに掃除を始めてしまうと、掃除機がけのときに物が邪魔になったり、細かいゴミやホコリを見逃したりしてしまいます。一時的でいいので、使っていないものや散らかっている物は別の部屋や箱に移動させましょう。例えば、雑誌、ゲームコントローラー、リモコン、おもちゃなどがよく床に置かれがちです。これらを一度どかして、スッキリした状態で掃除を始めると効率がグッと上がります。
片付けグッズを準備しておこう
スムーズに整理整頓を進めるために、片付け用のグッズを準備しておくと便利です。たとえば、仕分け用のカゴやボックス、ゴミ袋、不要品を入れる袋などです。「これは捨てる」「これは戻す」「これは迷ってる」といった感じで分けながら進めると、あとからの作業も楽になります。また、掃除中にホコリが舞うこともあるので、マスクや使い捨て手袋があると安心です。準備が整っていると、途中で探し物をしたり、中断したりせずに一気に進められますよ。
「いる・いらない」の分別ルール
掃除ついでに断捨離もしたいときは、「3秒ルール」がおすすめです。手に取って3秒以内に「使う」「使わない」が判断できない物は、基本的に使わない物と考えてOKです。また、半年以上使っていない物や、同じような物が複数ある場合も、手放す候補になります。「いつか使うかも」は要注意ワード。結局使わずに場所を取ってしまうことが多いです。リビングは家族が集まる場所なので、常にシンプルで使いやすい空間に保つことが大切です。
収納場所は“使う場所の近く”が原則
片付けた物を戻すときには、「使う場所の近く」に収納するのがコツです。たとえば、リモコンはテレビの近く、読みかけの本はソファ横のカゴに入れるなど、物の“定位置”を決めておくと、自然と片付けやすくなります。家族みんなが使うリビングだからこそ、誰が見てもわかりやすい収納が理想です。「しまいやすい」「取り出しやすい」を意識して収納すると、散らかりにくい部屋になります。
モノを減らすと掃除がラクになる理由
リビングに物が多いと、掃除のたびにどかしたり戻したりする手間が増えます。そのため、物を減らすことは、掃除をラクにするための第一歩です。とくに床に物があると、掃除機がけや拭き掃除のときに障害物になってしまい、時間も手間もかかります。逆に、必要なものだけが置かれているスッキリとしたリビングは、掃除の効率もアップし、見た目も気持ちもスッキリします。まずは「1日1個捨てる」など、少しずつ物を減らす習慣を始めてみましょう。
上から下が基本!ホコリを効率よく落とす順番とは?
まずは天井・照明からスタート
掃除の基本は「上から下へ」です。なぜなら、上の方のホコリを落としてから下を掃除しないと、せっかくきれいにした床にまたホコリが落ちてしまうからです。まずは天井や照明器具をチェックしましょう。天井には目に見えないホコリが意外とたまっていて、特に照明のカバーやシーリングファンはホコリの溜まり場です。長いモップやハンディワイパーがあると、手を伸ばさずに高い場所も簡単に掃除できます。
壁・カーテンのホコリも見逃さない
壁やカーテンもホコリがつきやすい場所です。特にテレビの裏側や家具のそばにある壁は、空気の流れが少ないのでホコリがたまりがち。壁は乾いたマイクロファイバークロスで優しく拭くと、傷をつけずにホコリが取れます。カーテンは定期的に洗濯するのがおすすめ。難しければ、掃除機の布用ノズルでホコリを吸い取るだけでも違います。細かいところもきちんと掃除することで、空気がきれいになり、リビング全体がスッキリします。
家具の上部はホコリがたまりやすい
棚の上やテレビボードの上など、普段あまり目が届かない家具の上はホコリがたまりやすい場所です。気づかないうちにホコリが山のように積もっていることもあります。こういった場所はハンディモップや静電気でホコリを吸着するクロスを使うと便利です。また、物が置きっぱなしだとホコリがたまりやすくなるので、なるべく物を減らしてシンプルに保つこともポイントです。
テレビや家電は静電気対策も必須
テレビやスピーカー、ゲーム機などの家電は静電気の影響でホコリが吸い寄せられやすくなっています。これらの機器を掃除するときは、電源を切ってから柔らかい乾いたクロスで優しく拭くようにしましょう。アルコール成分入りのクリーナーを使うと、ホコリが付きにくくなります。また、ケーブル周りにもホコリがたまりやすいので、定期的に掃除を忘れずに。ホコリが原因で家電が壊れることもあるので、こまめなケアが必要です。
掃除機は最後!その理由とは?
掃除機は一番最後に使うのが正解です。というのも、上から順番にホコリを落としていくと、最終的に床にホコリがたまるからです。そのホコリを一気に吸い取るために、最後に掃除機をかけるのが効率的です。また、先に掃除機をかけてしまうと、途中で落ちてきたホコリを再び掃除する手間が増えてしまいます。しっかり手順を守ることで、リビング全体を無駄なくきれいにすることができます。
床掃除は順番が命!正しいやり方とコツを解説
フローリングの前にゴミを取り除こう
床掃除を始める前に、まず床に落ちている大きめのゴミや物を拾いましょう。これを省くと、掃除機がうまく動かなかったり、ワイパーにゴミがからまってしまうことがあります。特に小さなレゴやヘアピンなどは、掃除機が吸い込んで故障の原因になることも。目につくゴミは手で拾いながら、ゴミ箱にポイしておくのが安心です。このひと手間が、あとからの掃除をスムーズにしてくれます。
また、椅子や小さなテーブルなど動かせる家具は、できるだけ端に寄せるか持ち上げて別の場所に移動させておくと、床全体をしっかり掃除できます。全体が見渡せるようにしてから作業するのがポイントです。
掃除機とクイックルワイパーの使い分け
床掃除には掃除機とクイックルワイパーの両方を使うのが効果的です。最初に掃除機をかけて、大きめのゴミや髪の毛、ホコリを吸い取ります。ここでポイントなのは、「手前から奥に」「壁際も丁寧に」です。一方向にゆっくり動かすと、吸引力が落ちずに効率よくゴミを取ることができます。
掃除機の後にクイックルワイパーなどのシート型モップを使うと、掃除機では取り切れなかった細かいホコリや皮脂汚れがキレイに取れます。特にペットの毛や花粉が気になる季節には、この“ダブル使い”が効果絶大です。使い捨てシートは、汚れたらすぐ交換するのが基本。無理に使い続けると汚れを広げてしまうこともあります。
拭き掃除は“二度拭き”が鉄則
フローリングの床を拭き掃除する場合は、「二度拭き」が基本です。最初に水拭きをして、皮脂や食べこぼしの跡などをしっかり落とします。その後、乾いた布やモップで乾拭きすると、水分がしっかり取れてベタつきやカビを防げます。
特に子どもやペットがいる家庭では、床を舐めたり寝転んだりすることもあるので、安全な天然成分の床用クリーナーを使うのが安心です。市販のフローリング用ワイパーにも二度拭き対応のタイプがあるので活用してみましょう。
床の素材に合った洗剤選び
床の素材によっては、使ってはいけない洗剤があります。たとえば、フローリングにアルコール入りの強い洗剤を使うと、表面が傷んでしまうことがあります。逆に、タイルやクッションフロアの場合は中性洗剤やアルカリ性の洗剤が効果的な場合も。
わからないときは、製品に書かれている「使える床材」を確認したり、目立たない場所で試し拭きしてから使うと安心です。間違った洗剤選びは、ツヤがなくなったり変色の原因になるので注意しましょう。
「週1回」でもきれいが続く習慣術
毎日床掃除をするのは大変ですが、ポイントを押さえれば週に1回でも十分きれいを保てます。たとえば、日々のゴミやホコリはハンディワイパーでサッと拭き取り、週末にしっかりと掃除機+拭き掃除をする習慣をつけると◎。曜日を決めて「日曜は床掃除の日」とスケジュールに組み込むのも続けるコツです。
また、玄関でスリッパに履き替えるなど、そもそも床が汚れにくい習慣をつけるのも有効です。小さな工夫の積み重ねで、掃除の回数を減らしても清潔なリビングを保てます。
忙しくても続けられる!時短掃除のテクニック
5分で終わる朝のリビングリセット
朝の5分を使って、リビングをサッと整える「朝のリセット」は時短掃除に最適な方法です。例えば、クッションを整える、ブランケットを畳む、テーブルの上の物を元に戻すだけでも、かなりスッキリします。毎朝この小さなルーチンを作ることで、散らかりにくい部屋に近づきます。
この習慣は、出勤・登校前の“スイッチタイム”としてもおすすめ。たった5分でも、心地よい空間をキープできる効果があります。タイマーを使って「よーい、スタート!」とゲーム感覚でやるのも楽しいですよ。
家族と分担すればグッと楽になる
掃除は一人でやるより、家族と協力するとグッと楽になります。「子どもはおもちゃの片付け担当」「パパは掃除機係」など、役割を分担するだけで、短い時間でも部屋全体がキレイになります。
特に週末は“家族で掃除タイム”を設定して、一緒に作業するのがおすすめ。掃除のあとにおやつタイムやゲームタイムを作ると、家族みんなのモチベーションもアップします。
スケジュール化で掃除忘れを防ぐ
掃除の習慣化には、スケジュール管理が効果的です。スマホのカレンダーアプリに「毎週金曜日は床掃除」などとリマインダーを設定しておくと、うっかり忘れることがなくなります。
また、月ごとに「照明掃除」「カーテン洗濯」など、リビングの掃除項目をローテーションするのもおすすめ。やることが明確になることで、掃除へのハードルがグッと下がります。
掃除道具は“手が届く場所”に置くべし
掃除道具が取り出しにくい場所にあると、つい掃除を後回しにしてしまいます。たとえば、リビングに使うハンディモップやワイパーは、すぐ手が届く収納に置いておくのが◎。おしゃれな掃除道具をリビングの隅に置くのも手です。
また、掃除シートなどの消耗品はストックを切らさないようにしておくと、思い立ったときにすぐ掃除ができます。出しやすさ=続けやすさ、と覚えておきましょう。
自動掃除機を上手に活用する方法
忙しい人にとって、ロボット掃除機は強い味方です。特に共働き家庭では、出かけている間にリビングを掃除してくれるので大助かり。けれど、部屋が散らかっているとロボットが動きにくくなるので、前もって床に物を置かない習慣が必要です。
また、椅子の脚に引っかからないように工夫したり、タイマー設定を活用するとより効率的。ロボット掃除機を“掃除のサポーター”として使えば、時短ときれいの両方を手に入れられます。
掃除が続かない人へ!楽しく続けるコツと習慣化
「完璧にやらない」が続けるコツ
リビングの掃除を毎日続けるのは、実は「完璧を目指さない」ことが大事です。「全部ピカピカにしなきゃ」と思うと、面倒になってやる気がなくなってしまうことがよくあります。だからこそ「今日はテーブルの上だけ」「今日は床の拭き掃除だけ」など、気楽にやるのがコツです。
掃除は“やらない日がある”のではなく、“できる範囲でやる日がある”と考えると、気持ちもずっとラクになります。「今日は5分だけやって終わり」でも十分。少しでも前に進んでいればOKという考え方が、続けられる秘訣です。
お気に入りの音楽で気分を上げる
掃除の時間を「楽しい時間」に変えるには、音楽の力を借りるのが効果的です。好きな音楽をかけながら掃除をすると、気分が上がって自然と体も動きます。テンポのいい音楽をかけるとリズムに乗って掃除もはかどります。
プレイリストを作って「この曲が終わるまで掃除する」など、自分ルールを決めると、ゲーム感覚で楽しく続けられます。また、ポッドキャストやラジオを聴きながらの“ながら掃除”もおすすめです。
終わった後のスッキリ感を味わおう
掃除が終わった後の「気持ちいい〜」という感覚を、ちゃんと味わうことも習慣化のコツです。リビングがきれいになると、自然と心も落ち着き、リラックスした時間が過ごせます。その気持ちよさを自分の中でしっかり感じることで、「また掃除したいな」と思えるようになります。
終わったあとにお気に入りの飲み物を飲む、アロマを焚く、ふかふかのクッションでくつろぐなど、“掃除のごほうびタイム”をセットで用意するのもおすすめです。
Before→Afterの写真でモチベUP
掃除前と掃除後の写真を撮って見比べると、「自分って頑張ったな!」という達成感が味わえます。特に片付けや断捨離をしたときは、変化が目に見えてわかるのでやる気がぐんとアップします。
写真はスマホで簡単に撮れるので、定期的に記録しておくと、掃除のモチベーション維持にぴったりです。SNSに投稿したり、家族と見せ合ったりするのも楽しいですね。
習慣にするための「トリガー行動」
掃除を習慣にするには、「何かのついで」にやるのがポイントです。たとえば「朝ごはんのあとにテーブルを拭く」「帰宅したらすぐにクッションを整える」など、すでに習慣化されている行動とセットにすることで、掃除も自然と続けられるようになります。
これを“トリガー行動”と呼びます。新しい習慣を身につけるには、このトリガーをうまく使うことがカギになります。「毎日〇〇のあとに掃除」と決めるだけで、無理なく習慣化できるのでぜひ試してみてください。
まとめ
リビングの掃除は「順番」がとても大切です。
まずは整理整頓から始めて、上から下へホコリを落とし、床掃除は最後に丁寧に行うことで、効率よくきれいな空間を作ることができます。また、掃除は「完璧を求めすぎず」「無理なく続ける」ことがコツです。
日々の暮らしの中で掃除を“苦手なもの”ではなく“気持ちがスッキリする時間”として捉え直すことで、家族みんなが過ごしやすいリビングが手に入ります。ぜひ今回紹介したテクニックや習慣化のコツを取り入れて、あなたらしい“掃除スタイル”を見つけてみてくださいね。